冬の路面電車[市電・都電]情報
冬の観光をより楽しくする路面電車の活用術
バス、電車、レンタカーなどと並んで交通手段のひとつである路面電車。気軽に利用できる路面電車は、都市部の観光をする際の交通手段として便利であり、徒歩観光が辛い冬の有力な移動ツールです。また、レトロな雰囲気が漂う路面電車の車窓から見る風景は、普段より少し特別なものとして目に映ります。
観光先が都会なら路面電車を賢く利用

観光先の交通手段として便利なもののひとつにレンタカーがあります。しかし、東京や大阪などの都会の場合、必ずしもレンタカーが便利とは限りません。都会でレンタカーを利用した場合、運が悪ければなかなか駐車場が見つからずに時間を浪費してしまうというデメリットが発生します。また、都会のコインパーキングは郊外に比べて駐車料金の設定金額が高いことがほとんどですので、行く先々でかかる駐車料金だけでもかなりのコストに。路面電車を利用した場合、長い区間の乗車でも一律料金なのが魅力です。1日乗り放題のフリーパスも各社で販売されているので、乗り降りの多い観光の際に利用することで、さらにお得に移動することが可能。時刻表通りに目的地へ着くことができるので時間も無駄にならず、有効に使うことができます。以上のことから、都会で早く、安く、賢く観光するのなら路面電車を利用するのがお得。また、普通の電車やバスなどにはないノスタルジックな雰囲気が味わえるのも、路面電車ならではの魅力と言えます。
路面電車で巡る冬の東京ツアープラン
都内を走る「都電荒川線」は、東京の下町・荒川区から新宿区早稲田までを結ぶ、都内に現存する数少ない路面電車のひとつです。「飛鳥山」を降りてすぐにある「飛鳥山公園」は、桜の名所として名高い公園。春の桜も有名ですが、実は冬にも咲き誇る冬桜が見られるスポットでもあるのです。この公園に植えられているのは、春と冬の年2回花を咲かせる、珍しい「十月桜」という品種。冬の見頃は10~12月頃で、淡いピンクのかわいらしい花を咲かせます。「飛鳥山」から三ノ輪橋方面へ乗車し、「荒川車庫前」を下車してすぐの「都電おもいで広場」には、過去に使用されていた旧型車両の展示がされており、都電荒川線の歴史に触れることが可能です。ひとつ隣の「荒川遊園地前」にあるのは、大正11年に開園した東京23区で唯一の区営遊園地である「荒川遊園」。コンパクトな遊園地のため、冬の寒空の下でも長距離を歩く必要がないのがポイントです。こぢんまりとしながらも、低年齢の子どもが楽しめるアトラクションがたくさんあるので、子連れ観光の際には併せて訪れると親子とも楽しめます。きらびやかな最新の観光スポットを巡るのも良いですが、1両編成のレトロな路面電車にゆったりと揺られながら、昔ながらの風景が残る東京の下町を眺める散歩旅はいかがでしょうか。
路面電車で巡る冬の大阪ツアープラン
大阪には天王寺~堺の間を繋ぐ大阪唯一の路面電車「阪堺電気軌道」があります。日本一高いビル・あべのハルカスや、「すみよっさん」と呼ばれ大阪の人々から親しまれている住吉大社、通天閣のある新世界などへのアクセスに富んだ電車です。大阪の都市部の景観を彩るのは、「天王寺駅前」から「阿倍野」間の線路移設に伴って作られた関西初の芝生軌道。路面電車で南下すると陰陽師で知られる安倍晴明神社や、かつては熊野神社の分霊社であった阿倍王子神社など、由緒ある神社仏閣が数多く点在しています。中でも「住吉鳥居前」はその名の通り、路面電車を降りるとすぐ目の前に住吉大社が迫る電停。電停からでも入り口の鳥居が目に留まるほどの近さにあり、大社に沿って路面電車の軌道が走っているため、年明けには初詣の参拝客で賑わう住吉大社の荘厳とした雰囲気を車窓からでも感じることができるのが魅力です。「恵美須町」方面へと折り返すと、大阪のシンボルでもある通天閣を車窓から望むことができます。通天閣のそびえる新世界エリアは名物の串カツのお店が軒を連ねており、寒い冬の日に熱々の串カツを食べるのもまた一興。大阪の街は熱々なグルメがたくさんあるので、寒い冬の日には大阪を路面電車で探索しながらおいしいものを食べ歩くのもおすすめです。



クリスマスに大晦日、正月、バレンタインと冬は行事が目白押し。国内のいくつかの都市では、季節のデコレーションを施した車両を街中で見かけるなど、路面電車も街の雰囲気を盛り上げるのにひと役買っていると言えます。クリスマスシーズンには乗務員がサンタクロースに扮しているなど、思わず笑顔になれる路面電車へ今年も乗りに行きましょう。
街中を彩るクリスマス電車

クリスマスシーズンには特別仕様にアレンジされる路面電車もあります。運良く乗車できた人はもちろん、偶然にそばを通り抜けたときには、心を和ませてくれます。実施の有無や詳細は年によって異なるので、各年の発表内容をホームページなどでチェックしてみましょう。
広島電鉄のクリスマス電車
広島県の路面電車、広島電鉄では、毎年恒例のイベント電車「クリスマス電車」を12月中に実施。車両をガーランドやリースなどで華やかに装飾し、車外に向けてクリスマスソングが流れます。日が暮れたころから運行するのでロープライトの電飾がキラキラと輝き、車内外はロマンティックな雰囲気に。人気の高い電車だけに、近年では乗車するのに事前応募が必須。これまで乗車を楽しむ「乗合電車」、サンタクロースと一緒にイベントを行なう「イベント電車」、車内でクリスマスソングを流し、マイクの貸し出しなどを行なってくれる「貸切電車」の3つの形式で開催されました。
岡電のクリスマス電車
岡山県内を運行する路面電車、通称「岡電」(岡山電気軌道)でも「クリスマス電車」が人気。例年12月に実施します。通常の運行ダイヤのうち、特定の車両のみをクリスマス仕様にデコレーションするもので、車両の先頭にリースなどが飾られます。過去の出発式ではサンタクロースが現れ、子どもたちにグッズやお菓子のプレゼントを配ったこともあります。
札幌市電のクリスマスラッピング
北海道の札幌市電では、2000年(平成12年)12月からクリスマスをモチーフにしたラッピング電車が走行を開始。北海道コカ・コーラボトリングとのタイアップによるもので、デザインは毎年変更されてきました。車内もリースなどの装飾がなされているので、乗車するとさらにクリスマースムードを満喫できることでしょう。
年末年始は土日祝と同様!?
路面電車の運営会社によって異なりますが、12月末から正月三が日あたりまでは土日祝のダイヤ、あるいは臨時ダイヤが採用されるのが一般的。通常は土日祝のみ利用できる1日乗り放題チケットを購入・利用できることもあるので、年末年始の休みを利用して沿線観光をお得な料金で楽しむのもおすすめです。
初詣電車
路線によっては12月31日の大晦日などに初詣のための臨時運行が増発されることがあります。例えば、函館市電では通常は20時ごろ運行する路線において、大晦日の深夜に「初詣無料電車」を増発。しかも運賃が無料なので、多くの方が利用します。長崎県の長崎電気軌道でも、諏訪神社への参拝客に向けた初詣深夜運行を例年行なっています。
2月はバレンタインチョコの配布も
富山県の富山ライトレールと広島県の広島電鉄では、2月14日のバレンタインデーの時期に合わせたサービスを実施したことでも知られています。富山ライトレールでは、バレンタインデー当日にチョコレートを配布。チョコレートのデザインにも趣向を凝らし、愛らしいキャラクターを配するなど毎年注目を集めています。広島電鉄では車内の吊り革のうち、ハートの吊り革がひとつだけ混ざっているというバレンタイン・ホワイトデー向けのラッピング電車を運行させたことも。同電車では、バレンタイン当日と、ホワイトデーにもお菓子のプレゼントが配布されました。今年はどんなバレンタインサービスが、どの路面電車で実施されるのか期待が高まります。
路面電車は一般的な鉄道とは違い、道路の上に線路が敷かれた鉄道です。近年は自動車の普及や道路交通の渋滞などから、その役割は徐々に地下鉄へと移っていったところもありますが、現在でも約20の地域で路面電車が活躍しています。特に札幌や函館、福井、富山など雪の多い地域での運行が目立ちます。冬、暖かい車内から街の雪景色を眺めながら移動ができ、路面電車は、観光にはぴったりな交通手段ではないでしょうか。
北海道の除雪路面電車「ササラ電車」

札幌に路面電車が走り始めたのは1918年(大正7年)のことで、人々の足として非常に重宝されました。しかし、札幌は当時も今も豪雪地帯。冬になると除雪が追いつかず、運休に追い込まれたり、電車が立ち往生したりしてしまうことも多々ありました。そこで開発されたのが通称「ササラ電車」と言われる「ロータリーブルーム式電動除雪車」です。これは、1925年(大正14年)、路面電車を運営していた札幌電気軌道株式会社の技師長、助川貞利らによる研究によって生み出された除雪列車で、「ササラ」とは台所で使われていた竹製のたわしのことです。この台所用品がヒントとなり、車体の前後に取り付けたブラシ状の竹のササラを回転させて走行し、線路に積もった雪を掃き飛ばす仕組みを開発。ちなみに、ササラは「モウソウ竹」という日本で最大の竹を使っており、山口県の農村地域で農閑期の主婦たちがこのササラを作っていました。特注サイズになると長さ30センチ、直径3.5センチに及びます。現在、除雪専用電車であるササラ電車は、札幌と函館でしか見ることができず、毎年11月の終わりから12月頭になると、この電車の初出動の様子がニュースで取り上げられ、冬の始まりを知らせてくれます。北海道の冬の風物詩でありながら今なお活躍を続ける、頼もしい路面電車です。
厳しい寒さの冬にうれしい「おでんしゃ」
愛知県豊橋市内を走る屋台、「おでんしゃ」。これは、豊橋鉄道東田本線の路面電車内でおでんが食べられるサービスです。東海地方唯一の路面電車である豊橋鉄道は、私鉄であるにもかかわらず「市電」と市民から呼ばれるぐらい親しまれており、豊橋のシンボルとして活躍しています。そんな豊橋の「市電」で、2007年(平成19年)から冬季限定で行なっている人気のサービスが「おでんしゃ」なのです。冷えた生ビールを片手に、グツグツと煮えたおでんを食べながら、揺れる車窓から豊橋の冬景色を望むことができます。屋台の感覚で路面電車が楽しめるとあって、毎年多くの人が乗車しています。また、このおでんには豊橋の名物である「ヤマサちくわ」を使用。「ヤマサちくわ」は東海道五十三次の34番目の宿である吉田宿(豊橋市)にあった魚問屋が発祥のちくわ屋さんで、「昔も今も変わらぬ旨さ」のキャッチコピーのもと、豊橋名物として東海地方のみならず全国にも名が知られています。元々「おでんしゃ」のおでんにヤマサちくわは使われていませんでしたが、「豊橋の路面電車ならヤマサのおでんが当然だろう」との市民の声が相次ぎ、「ヤマサちくわ」を使うようになりました。2015年(平成27年)3月には、岡山電気軌道の路面電車でも、「おでんしゃin岡山」を運行し、豊橋とまったく同じヤマサちくわのおでんを提供。岡山では「おでんしゃ」の発表後、すぐに申込みが満員になる程の人気ぶりで、今後も「おでんしゃ」は続いていきそうです。
鉄道や車など、乗り物の技術は日進月歩で進歩しており、路面電車も例外ではありません。近年では、乗降に優しい超低床車両が採用されるなど、超高齢化社会を迎える中で、路面電車は今後も都市交通の一躍を担う可能性があります。また、路面電車と鉄道の長所を取り入れた「ライトレール」も注目されています。次世代の路面電車が、新しい夢を叶えてくれるかもしれません。
超低床車両

近年の路面電車は技術開発が進み、「超低床車両」が採用されています。超低床車両には、車内中央通路が全長にわたって100%低床化されている「完全低床」と、100%未満の「部分低床」があります。また、床面の高さは地上から30~35cmと車内床面の高さが極端に低く、プラットホームに止まるとほぼフラットになるように設計してあります。これにより、乗降でのバリアフリー化を実現し、高齢者や障害者でも容易に乗り降りができるようになりました。また、車イスでもスムーズに乗降できるため、現在走っている多くの路面電車がこの超低床車両を導入しています。従来の車両は、車輪と動力装置が床下にあったため、床面をあまり下げることができませんでしたが、超低床車両は、車輪の直径を小さくして、左右の車輪を繋ぐ車軸を廃止した「左右独立車輪式」を採用し、動力装置などの電子機器を車両上部に配置することによって、超低床車両を実現しました。東京都の都電のように、超低床車両を用いず、プラットホームの高さを高くすることで、バリアフリー化に対応しているケースもあります。
超低床車両は一般的な電車に比べると窓が広く、快適性やデザイン性、静粛性にも配慮がされており、二酸化炭素などの有害物質を排出しないため、地球温暖化を抑制する新たな交通システムとしての位置づけが強まっています。
路面電車とライトレール
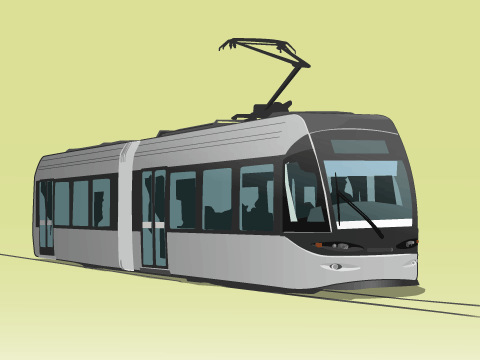
地球温暖化問題から、二酸化炭素を排出しない路面電車が改めて見直されており、欧米では都市部の新しい交通システムとして活躍しています。アメリカでは、大陸横断鉄道のような大規模な列車ではなく、軽量で車両数も少ない鉄道が各都市で運行しています。このような路面電車を「ライトレール」と呼んでいます。主に都市部を走り、路面電車のようにプラットホームが低いものや、一般の鉄道のように高いものもありますが、車両は小型で短距離の路線を持つのが特徴です。また、駅間も短く、プラットホームも簡易的なものとして建設コストを抑えています。路面電車と一般の鉄道の長所を取り入れ、新しい都市鉄道として注目されています。
日本でもライトレールに相当する車両がありますが、ほとんどのプラットホームは高い状態で、鉄道として分類されています。
路面電車は、車両面では進化しているものの、他の交通機関との共存や連携を含めたシステムの整備には課題を残しており、これからの都市交通のあり方が求められています。
チンチン電車の由来
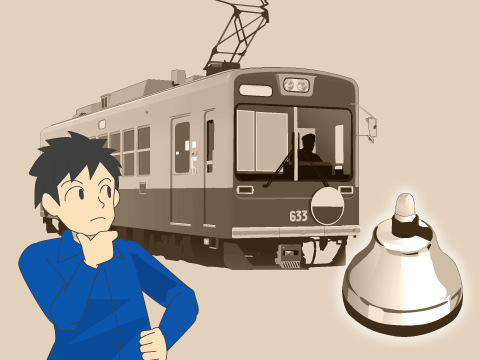
路面電車を「チンチン電車」と呼んでいた時期がありました。この「チンチン電車」の名前の由来には諸説があり、走行中、運転士が乗客や通行人に対して、ベルを鳴らして警告した音に由来する説と、車掌と運転士が合図を送るために鳴らしていたベルの音に由来する説があります。ベルの音にはそれぞれ意味があり、「チン」と1回鳴らすと停車するための合図、「チンチン」と2回鳴らすと停留所を通過するための合図となり、停車中に2回鳴らした場合は、出発の合図となります。また、「チンチンチンチン」と3回以上の連打した場合は、非常停車を意味します。
ベルの代わりにブザーが鳴る車両もありますが、今でも、昔ながらのベルを使用している車両もあります。









