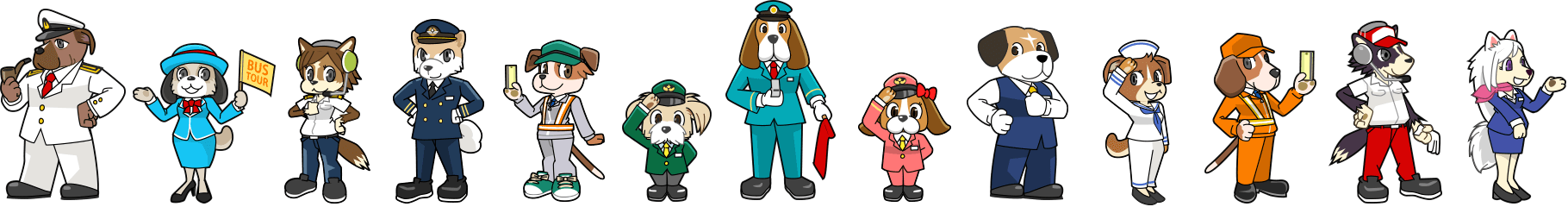路面電車[市電・都電]用語辞典
![路面電車[市電・都電]用語辞典](/glossary/assets/image/img-main-visual-pc.jpg)
![路面電車[市電・都電]用語辞典](/glossary/assets/image/img-main-visual-sp.jpg)
![]()
- 小
- 中
- 大
-
軽便鉄道
けいびんてつどう軽便鉄道とは、通常の電車に比べて小規模で安価に造られた鉄道のこと。狭義には、「軽便鉄道法」(1910年〔明治43年〕公布〜1919年〔大正8年〕失効)に基づいて建設された鉄道を指すが、広義には鉱山鉄道や殖民軌道など同法に当てはまらない鉄道も含まれる。1890年(明治23年)代〜1900年(明治33年)代にかけて京都市、名古屋市、東京都に路面電車が開業して路線を拡大する一方で、日本各地に様々な軽便鉄道が開業した歴史がある。そうした鉄道は車両が小型でレールの幅が狭く、走行スピードが遅かった。乗合バスの普及などが原因で徐々に消えていき、2016年(平成28年)10月時点で現存するのは富山県の「黒部峡谷鉄道」などわずかである。
全国から路面電車[市電・都電]を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の路面電車[市電・都電]を検索できます。