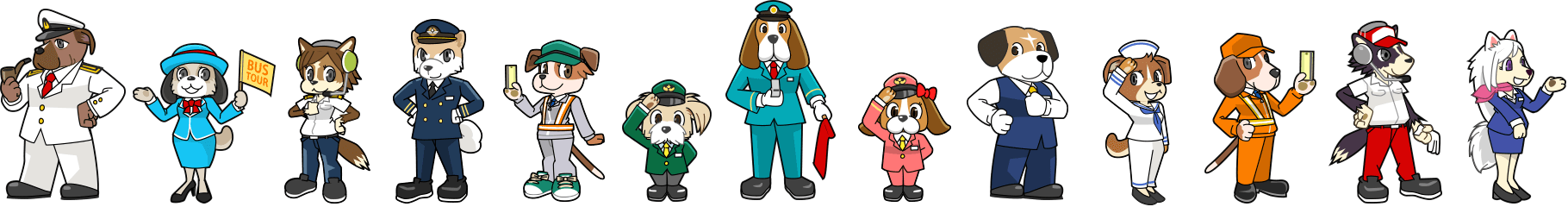路面電車[市電・都電]用語辞典
![路面電車[市電・都電]用語辞典](/glossary/assets/image/img-main-visual-pc.jpg)
![路面電車[市電・都電]用語辞典](/glossary/assets/image/img-main-visual-sp.jpg)
![]()
- 小
- 中
- 大
-
吊り掛け
つりかけ吊り掛けとは、電車のモータを台車に装着する方式のひとつ。「吊掛式(ノーズサスペンション)」、あるいは「吊掛駆動方式」の名称の一部である。米国人の電気技術者・発明家「フランク・ジュリアン・スプレイグ」が、1888年(明治21年)に彼が建設して営業したヴァージニア州リッチモンドの市電の車両用に開発した技術。構造としてはモータを台車に吊り掛けるイメージで、「ノーズ」と呼ばれる突起をモータに2方向取り付け、そのうちのひとつは車軸に乗せ、もうひとつはバネなどの緩衝材を媒介にして台車枠に取り付ける物である。平歯車で動力を伝えるシンプルな方式で、レールからの衝撃がモータに直接伝わるなどの欠点があったが、開発当時には画期的な技術だった。この吊掛式は、PCCカーの登場まで長く、電車のモータ駆動方式のスタンダードとなっている。
全国から路面電車[市電・都電]を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の路面電車[市電・都電]を検索できます。